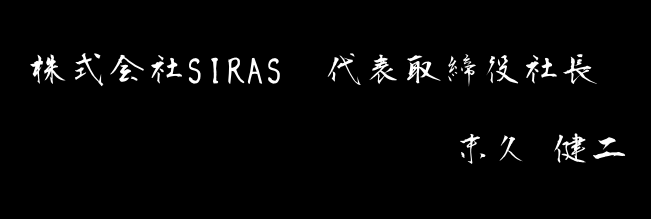暗闇の中、歩くしかなかった20代

IT技術者として働きはじめた頃、私は自信も実力もなく、ただ目の前の業務をこなすことで精一杯でした。
下請けとして怒鳴られ、ブラックな環境で心身はすり減っていく。そんな日々の中で、ある案件で大きな失敗をしてしまい、客先から激しく責められたその瞬間、何かがプツンと切れるような感覚がありました。
「もう無理だ」「この仕事には向いていない」そう思った私は、技術の道を捨て、現場を離れました。
基礎から学び直した、もうひとつの技術者人生
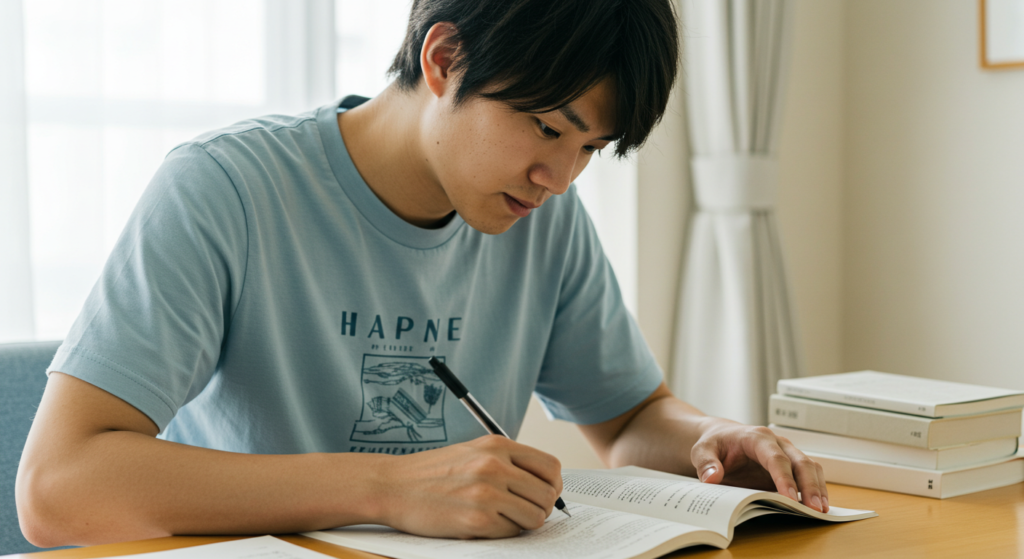
現場を離れた私は、派遣やアルバイトを転々とする中で、偶然複数の恩師たちと出会いました。
その恩師たちは、高度成長期時代、大手メーカーで働いており、最先端のアーキテクチャーを命をかけて習得された方々です。
恩師たちは私に、「技術以前の基礎力」を徹底的に叩き込んでくれました。小学生レベルの国語からやり直し、母国語の訓練、具体と抽象の往復、伝える力――基礎の徹底的な底上げから、人生が変わり始めたのです。
そこで出会ったのが、「構造化設計」という技術でした。
これは、1970年代ごろに提唱された設計手法で、当時のソフトウェア開発の混乱を整理するために生まれたものです。
今でこそ構造化設計は「古いもの」「時代遅れ」と見なされがちですが、私は全くそうは思いません。
むしろ、それこそがすべての設計の“原点”だと考えています。
技術や手法は進化しても、品質の高い設計構造、伝える力、全体を俯瞰する力──
そうした基礎こそが、設計の本質であることは、何も変わりません。
中でも大きな影響を受けたのが、Tom DeMarcoの『構造化分析とシステム仕様』という書籍です。
DeMarcoは、ソフトウェア工学の黎明期において、構造化分析を体系化した人物であり、
「全体構造を見よ。情報(データ)の流れを明確にせよ」の旨のことを説いていました。
「設計とは、他者に正しく伝えるための構造である」──その思想は、今なお色褪せることがありません。
私はこの考えに出会い、ひたすら図を描き、つなげるという反復訓練を重ねる中で、
設計という行為が、なぜ存在し、どんな“本来の存在意義”を持つのか――その本質を、ようやく実感できるようになったのです。
特別な才能がなくても、継続し続けていけば、本質は必ず見えてくる。
今ではそう確信しています。
高度な手法ばかりが先行し、“土台”が失われている

現在の現場では、「ドメイン駆動設計」や「クリーンアーキテクチャ」など、
高度な手法やフレームワークが良い設計手法として、活用されています。
しかしその一方で、前提となる“構造的な思考”や“伝える力”が置き去りにされていることも少なくありません。
専門用語ばかりが飛び交い、読みにくく、保守しにくいコードや設計が量産される。それが、今の現場で多くの人を疲弊させている原因のひとつだと、私は感じています。
構造化設計で設計した洗練されたコードは、誰が見ても理解できるのです。技術者だけでなく、テスターやマネージャー、経営者等の非技術者でも概ね理解できるのです。
だからこそ私は確信しました。「時代が進んだからこそ、原点に立ち返る必要がある」と。
構造でつなぎ、感謝と一体感で仕事をする

SIRASは、技術・思考・伝達の“構造”を支えることで、「シンプルに理解でき、お互いが協力しやすい場」を当たり前にすることを目指しています。
そしてもう一人、私が深く尊敬している人物がいます。
日本の技術者・登山家であり、品質管理の先駆者でもあった西堀栄三郎氏です。
彼は、「感謝と一体感のない現場に、真の創造は生まれない」旨のことを語っています。
今でこそスクラム開発やアジャイルが“チームの信頼や共創”を重視するようになりましたが、
その本質を百年前から実践していた日本人がいたことを、私は強く伝えたいと思っています。
構造でつなぎ、心で育てる――
技術とは、そうあるべきだと私は信じています。
SIRASは、その“人と技術の原点”を、今の時代にもう一度取り戻していきます。